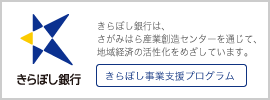SIC職場リーダー養成塾
SIC職場リーダー養成塾
受講者の声
- K社:H・Sさん
-
閑散期に別現場・別作業に取り組む作業者が、慣れない作業へのストレスを抱えており、その原因の一つとして「作業の属人化」が考えられた。
対応出来る作業者を増やすために、リーダー養成塾で身に学んだ「巻き込み力」を意識して、他者とのコミュニケーションの取り方や問題の抽出方法を見直しながら課題解決プロセスを進めていき、スキルマップ作成や作業者同士でのレクチャーを実施した。
特に、コーチング技法を取り入れて現場全体で課題解決のアクションプランを共有し続けたことで、作業者が自らの意見や考えを積極的に発言してくれるようになった。
確実に取り廻せる作業者の増加したことで業務が平準化されていき、作業者へのストレスを軽減する事が出来た。
- R社:S・Yさん
-
私は開発部門の責任者になったが、責任や役割を十分に理解していないことで本来すべきマネジメント業務に向き合えていなかった。
リーダー塾では、最初に管理職としてのコミュニケーションや課題解決手法について学び、自分が責任者として「何をすべきか?」日々考えながら行動した。一つは、社内では教育活動の中で傾聴を意識したコーチングを実践し、周囲を巻き込む力を磨いていったことで、業務を一任することができるようになってきた。もう一つは、リーダー塾での現状分析や数値目標など課題解決プロセスを通して、会社の利益を日々意識するようになった。
現在では、チーム一丸となってスキルを高めながら、課題に取り組む体制や品質向上に努めており、責任者としてのリーダーシップ力を発揮できるようになってきた。
- T社:K・Nさん
-
生産中に起こる機械トラブルに対しての復旧作業が部下だけでは出来ず、チョコ停や不良品が発生し、生産効率が落ちていた。
リーダー塾での実践期間中に、コーチングで学んだ傾聴や質問を生かして、部下に教育を行った。オープンな質問により部下の考える力を引き出し、傾聴では相手の立場に立って直ぐに意見を言わず、相手に考える時間を与えるように心掛けた。
その結果、「どうすれば機械が復旧出来るのか?」や「どのような原因で機械が止まったのか?」など、部下が自分自身で考えて積極的に取り組むようになった。
現在では、部下だけで機械トラブルを復旧出来るようになり、さらに、不良品の発生率が減ったことで以前より仕事に対して自信を持って取り組む姿を垣間見ることが出来た。
- R社:O・Dさん
-
新規受注の製造過程で、納期遵守への意識が低いメンバーがおり、製造工程に遅れが生じ、スケジュールに影響を及ぼしてしまうことがあった。
対策として、本塾で学んだ傾聴、質問、承認を活用してコミュニケーションを意識しながらメンバーと毎日ミーティングを行い、進捗状況を確認するようにした。
毎日コミュニケーションを取ることによって、次第にメンバーの方から進捗報告も含めて自発的に話すようになった。また進捗の内容も「~すれば出来そう」など前向きな報告をしてくれるように変わっていった。
その結果、以前より社内の雰囲気も良くなり、メンバーが常に相談や報告をするような信頼関係も築けたことで、生産性を高めるための良い影響を社内に与えている。
- M社:T・Kさん
-
私は部門責任者として次世代リーダー候補の育成が喫緊の課題であるが、ジェネレーションギャップが円滑なコミュニケーションを阻害していた。
本塾での実践期間中、コミュニケーション能力向上の方法や問題解決力を学び、周囲を巻き込みながら課題を解決するスキルを習得した。それらのスキルを活かして世代や年齢の違いを問わず、リーダー候補者たちと積極的に意見交換を行い、必要に応じて他部署とも連携しながら解決策を模索した。
その結果、リーダー候補者たちと円滑に対話でき、信頼関係を深めることができた。
リーダー候補者自身もリーダーとして必要なスキルや姿勢について学び、課題解決に向けた具体的なアプローチ方法や主体的に考え行動する力を身につけることができた。
- M社:Y・Aさん
-
製造部内では、不具合に対する原因を明らかにできていない事案が発生していることで、取引先に不具合品が流出するなど営業業務にも悪影響を及ぼしていた。
リーダー塾での改善案件として、不具合の多い特定の製品にターゲットを絞り不良数削減の改善をする目標を立てた。まず、作業者に「コーチング」を実施しながら本当の原因追及をして、課題に対しての具体的な行動計画を立てて実施した。
その結果、効果測定として数値目標に設定した不具合発生件数まで抑える事が出来たので、他の製品にも水平展開して製造部全体の不具合品低下に努めていく予定である。
作業者を巻き込みながら改善活動を進めたことで作業者自身の不具合に対する意識が変わっていき、結果として会社全体で不具合品の削減に繋がった。
- G社:N・Yさん
-
総務部では、メンバーの高年齢化が進むなかで体調不良等を理由に欠勤するケースも増えているが、業務範囲が広いこともあって属人化が進んでいた。
リーダー塾で取り組んだコーチングやディスカッションを活かして、上司と部下の困っている現状を明らかにした。それらを課題解決プロセスに落とし込み、対策として作業分担表に反映した作業マニュアルの作成し、部下に対して教育して作業評価を実施することで、総務部のスキルの底上げに務めた。
新たな作業ができるようになったことで部下の仕事への意欲が高まり、それが作業効率の向上につながった。さらに、総務部の教育システムの構築に部下も自ら進んで協力するようになった。
- O社:T・Kさん
-
営業は、本来外に出て新規の引き合いや情報を得るのが理想であるが、事務作業などに時間を取られ、営業活動に専念できていなかった。解決策として社内で支援する部隊が組織されたが、効果を見い出せていなかった。
本塾でのグループディスカッションや個別指導で学んだ、問題への取り組み方や解決の手法等、或いは、コミュニケーション手法を活用し、まず業務フローや人員構成図など利用して状況を整理した。そして、連関図などで問題の分析を行うことで、効果が不十分である原因を明らかにした。
課題解決に向けてこれから具体的なアクションを設定していくが、今後営業として機能していくために講じていく対策に対し、課員への理解や調整を図ることができた。
- C社:P・Sさん
-
台湾販売担当となったが、販売拡大のために担当部署内で具体的な営業戦略を策定することができておらず、台湾現地代理店任せの営業活動になっていた。
SICリーダー養成塾では、現状把握から行動計画までの一連の課題解決プロセスやコミュニケーション力を高めるコーチング技法等への理解を深めた。チーム内で「計画」→「実行」→「評価」→「行動」のPDCA サイクルを実現するために、学んだことを活用しながら定例ミーティングを通してやるべき仕事をリストアップし、チーム内で仕事を分担した。
メンバーが計画どおりに業務が進んでいない場合でも、私自身がリーダーシップ力を発揮してチームで仕事の調整を行うことで、営業目標達成に向けて効率的かつ効果的に業務を進めることができるようになった。